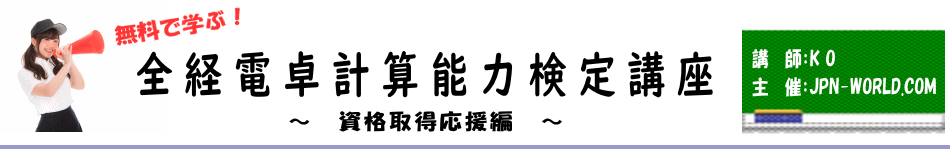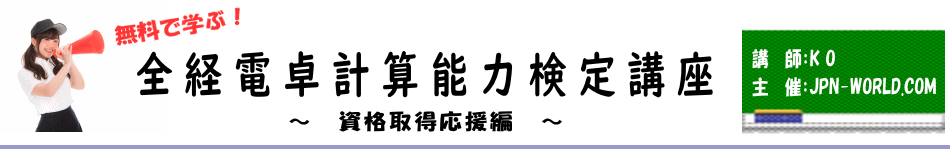皆さん、こんにちは。KOです^-^。今回はメモリ機能以外の機能についての内容です。ここでは私が長年愛用しているカシオの電卓(CASIO AZ-205A)を例に説明していきたいと思います。普段から使用している標準的な機能についてなので、気軽に読んでいただければと思います♪それでは、今回も頑張っていきましょう!
| 【今回の講座内容】 |
■「テンキー(00、0〜9)」「+」「−」「×」「÷」「=」「.(小数点)」の機能
■「AC」「C」「→」(削るマーク、機種によって表示は異なる)の機能
■「%」「√」の機能
■ラウンドセレクター(F、CUT、5/4)と小数点セレクター(5、4、3、2、0、ADD2)の機能 |
■「テンキー(00、0〜9)」「+」「−」「×」「÷」「=」「.(小数点)」の機能
これらの機能については、誰もが知っていると思うので、特に説明することはありませんが、電卓によって「00」というキーがついている場合があります。私はこの「00」のキーを初めて見た時、「このキーは必要ないだろう(笑)」と思っていましたが、上級を目指していると、「少しでも速く!」という気持ちが生まれ、自然に「00」のキーを極めようと考えるようになりました。うまく、使いこなせるようになれば武器になるので、上級レベルを目指すのであれば、慣れておくと良いでしょう。ただ、3級レベルでは特に必要ありません。
■「AC」「C」「→」(削るマーク、機種によって表示は異なる)の機能
この3つのキーは全て削除に関するキーになります。まず、「AC」についてですが、これはALL CLEARの略で、その名の通り、全てクリアするという意味になります。それに対し、「C」はCLEARの略で一部分をクリアするという意味になります。ただ、これだけでは分かりにくいので、この二つの違いについて見てみましょう。
【問題】 例)11+22+33
これは簡単(^-^)と思ったところ、誤って11+22+44と押してしまいました(-.-;)。さて、この状況でどのキーを押せば、一番効率がよく計算し直すことができるでしょうか?
ここで慌てて「AC」を押してしまうと、計算したもの全てがクリアになってしまい、一から計算をし直すことになります。この例では、ミスする前までに計算したものは11+22のみですが、検定では計算数が多く、特に後半で「AC」を押してしまうと、致命的なミスになりかねません。
では、こういった場合にはどうしたらよいのでしょうか? そうです!ここで役立つのが「C」のキーです。このキーは、先程も説明したように、一部分をクリアするキーになります。今回の場合だと、44と押した時点で「C」を押せば、44だけがクリアになります。そこで、正しい33を押し直して「=」のキーを押せば、その前に計算した11+22はそのまま消えないで記憶されているので、66と正しく計算されます。
ただ、ここで注意をしなければならないのは、これは、あくまでも「=」もしくは「+」を押す前の話になります。もし、「=」「+」を押してしまった場合は、その時点で計算されてしまいますので、「C」を押しても意味がありません。その場合は、誤って足してしまった分を引算して計算し直しましょう。もし、どの数字を押して間違ったのか不明な場合は、最初から計算するしかないでしょう。
では、次に「→」のキーについて説明します。電卓によっては「→」以外にも、右向きの三角の形をしたキーなどありますが、意味は同じです。このキーは下一桁の数字を削除する時に使える機能になります。「C」のキーと同様に、「=」「+」を押す前に使用できる機能になります。
例えば、55555を55557と誤って押してしまった・・・
この場合「C」でもOKですが、「→」を押すと、下一桁目から削除していくので、7を押す前の5555の状態に戻す事ができます。なかなか便利な機能なので個人的には好きです^-^ あと、これは好みによりますが、「C」と「AC」はどの電卓でも並んでいる配置されていることが多く、押し間違える危険性もあるので「→」で訂正する方が安全かもしれません。
 【ここでのPOINT】ミスした場合「C」「AC」「→」をうまく使いこなし、時間のロスは最小限に留める 【ここでのPOINT】ミスした場合「C」「AC」「→」をうまく使いこなし、時間のロスは最小限に留める
■「%」「√」の機能
「%」「√」についてですが、今回の電卓計算検定では使用しないので、簡単に触れることにします。ただ、「%」は知っておくと、日常生活でも、何かと便利かもしれません。
では、まず、「%」の使い方について説明します。ところで、皆さんは、まだ消費税が外税だった頃、この商品の消費税はいくらかかるだろうか?と、その場で消費税を計算したことはなかったでしょうか? 私はよくしていましたね。100円や200円なら、暗算でもすぐに分かりますが、これが9,980円や12,980円のように金額が大きくなると、計算が大変でした;;;。2019年10月からは10%となりますが、軽減税率制度も実施されるため、8%の商品と混在します。10%は暗算でも計算できるので簡単ですが、8%の計算は大変ですよね。
実はこんなとき電卓の「%」のキーを使うとすぐに計算がする事が可能です。例えば、12,980円の8%はいくらか計算したい時、12980×0.08と計算する方もいるでしょう。もちろん、それでも正解ですが「%」のキーを使用して、計算することも可能です。12980×8%と押し、あとは「=」を押すだけです。念の為、答えは1,038,4になります。簡単ですね!このように日常生活でも使用できるので、覚えておいて損はないですね^-^
では次に「√」についてです。「√」は私が中学生、高校生の頃に数学の平方根の計算問題で出てきた記憶はありますが、日常生活の中で、「√」のキーを使用して、何かを計算したことは「正直、一度もありません!」ということでこのキーは簡単に説明します。例えば、4の「√」を計算したい時、4と入力したあとに、「√」を押すだけで、答えの2という数字が出てきます。「=」を押す必要もありません。以上です^-^
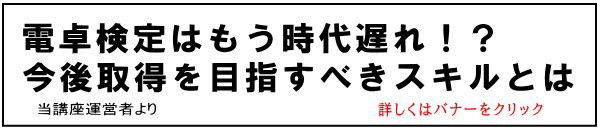
■ラウンドセレクター(F、CUT、5/4)と小数点セレクター(5、4、3、2、0、ADD2)の機能
まず、ラウンドセレクター(F、CUT、5/4)について説明します。「なんだこれ?」というふうに思う方もいるかもしれないですが、これらは小数点以下の表示をどのようにするかといった機能のことです。まず、「F」についてですが、これを設定していると、電卓が表示できる小数点以下の数字を全て表示します。つまり、フリーの状態であると考えれば、分かりやすいと思います。
次に「CUT」ですが、これは、小数点以下を指定する桁数まで表示し、他は切り捨てるという機能です。名前も「CUT」ですので、分かりやすいですね。
次に「5/4」についてですが、これは、小数点以下を指定する桁数まで四捨五入するという機能です。これも「5/4」という表示が、いかにも四捨五入という感じがしますね。
ところで、ここまで読んで「小数点以下を指定する桁数というのはどこで指定するの?」といった疑問を持った人もいるかもしれません。実は、その桁を指定する機能が小数点セレクター(5、4、3、2、0、ADD2)になります。
例えば11.23654という数字があったとします。これをラウンドセレクターを「CUT」に設定し、小数点セレクターを2に設定するとどうなるでしょうか?。「CUT」は小数点以下を指定した桁数まで表示し、他を切り捨てるので、この場合、小数点以下弟2位まで表示され、11.23となります。もし、小数点セレクターを3に設定すれば11.236、小数点セレクターを4に設定していれば11.2365となりますね。
では、同じく11.23654の数字を使って、ラウンドセレクターを「5/4」にして、小数点セレクターを2に設定するとどうでしょうか? 答えは11.24(小数点以下弟3位以下は四捨五入され、小数点以下弟2位までを表示)となりますね。
では、もう一つ、問題です。同じく11.23654の数字を利用し、ラウンドセレクターを「F」、小数点セレクターを4に設定した場合、どうなりますでしょうか。答えはそのまま11.23654になります。先程も説明したようにラウンドセレクターを「F」にしているので、いくら小数点セレクターを設定しても、何も変わりませんね!
 【簡単なまとめ】 【簡単なまとめ】
[例]157÷13
・Fで設定している場合
→12.0769230769・・・・(割り切れず。フリーの状態なので、電卓で表示できる桁数まで全て表示)
・CUT(小数点セレクター3で設定している場合)
→12.076(小数点以下第3位まで表示し、それ以外の第4位以下は切り捨てる)
・5/4(小数点セレクター3で設定している場合)
→12.077(小数点以下弟4位以下は四捨五入され、小数点以下弟3位までを表示) |
※電卓やメーカーによってはラウンドセレクターの中に、切り上げを意味する「UP」や「↑」がある場合もあります。
最後に「ADD2」という機能について説明します。これはアドモードといって、簡単に100分の1の状態で表示することができます。使い方は、ラウンドセレクターを「F」以外に設定し、「ADD2」を設定します。その状態で、例えば3と押して、「=」を押すと0.03のように100分の1で表示されます。もちろん、足し算も可能で4+3と押すと0.07と表示されます。主に通貨の計算などに使用されていますが、今回の検定では使用しないので、特に覚えるはないです♪
いかがだったでしょうか。電卓の機能についての内容はこれで終了です。次回の電卓のメモリ機能についてです。お楽しみに!
[最終更新日:2023年6月8日]
・サイドバーを含め、一部修正しました(2023年6月8日)
・スマートフォンでも見やすいように文字を大きくし、レイアウトを変更したほか、税率計算の事例を時代に合わせて変更しました(2019年8月25日)
・スマートフォンやタブレットでオーバーレイ広告が出ないように仕様を変更しました(2017年10月1日)
・2007年4月20日付けで公開していた内容をリニューアルしました。(2008年8月31日)
|